たとえば一枚のポスターや一本のCFが時代の空気を切り取り、その時代のシンボルになりえた時代が確かにあった。
1961年、サントリーが打ち出した「トリスを飲んでハワイへ行こう!」キャンペーンは、大ヒットとなり日本全国でトリスウィスキーが15億本売れたという。海外旅行が庶民にとって憧れの時代に、宝くじのような「夢」を与える広告だった。コピーを書いたのは、後に作家となる山口瞳。僕はリアルタイムでは4歳だから、キャンペーンそのものの記憶はないが、柳原良平のイラストと、渋い歌のCFはその後も長く続き、覚えている。うちの親父が毎晩飲んでいたのもサントリーだった。
70年代は、学生運動がつぶされて、みんなのベクトルが宙ぶらりんになっていて、振り返ると、挫折感を味わい首をうなだれた男たちの前に、すっくと強い意思を持つ女性たちが立っていた。広告では流通業界が元気で、特にパルコのポスターやCFは女性の自立を促して、エネルギーにあふれていた。そのポップなビジュアル表現とコピーは、石岡瑛子のディレクション。「裸を見るな、裸になれ」や「モデルって顔だけじゃダメなんだ」とか。女性の時代をきちんと掬い取って、それをカッコよくビジュアル化する。アートディレクターやグラフィックデザイナーが脚光を浴びた。時代を動かすかのような、その感覚が絶賛された。
時を同じくしてライフスタイルという言葉が市民権を持つようになり、生活提案型の広告がさまざまな分野に広がっていく…新たな生活提案によって、消費者の需要が喚起され、マーケットが拡大していく、どんどん拡大していき「モノ」が「しあわせ」と同じ価値観で語られる。
80年代は、その延長にありながら、生活提案がもっと「個人」に絞られていったように思う。「おいしい生活」や「好きだから、あげる」は、個人の感覚に着目して時代を切り取った好例だろう。糸井重里、仲畑貴志が頭角をあらわして、今まで黒子だったコピーライターという職業を全国的に知らしめた。
価値観の多様化という言葉とともに、個の嗜好性が尊重されつつも、ことモノを買うことになると、トレンドという歌い文句にみんなが踊らされた。地価が急激に上昇し、土地建物関連の成金が巷にあふれた。雑誌というメディアもいち早く反応し、さまざまな雑誌が発刊され、かたや潰れ、メディアが核分裂しはじめた。
都会の真っ只中でバブルを経験しながら、何だかなぁ、という思いが僕にはあった。六本木で遊びながら、ゴルフ三昧をしながら、ちょっと待てよ。僕もふくめて、みんな狂ってるよ、おかしいんじゃないの? で、1990年、バブル崩壊の前夜、僕は東京に見切りをつけて信州へ脱出した。
90年代は、「モノ」が売れない時代。「モノ」を買わない時代になった。地方都市に移り住んだ僕を待っていた仕事は、そのほとんどが「モノ」ではない広告だった。企業の会社案内や採用案内であったり、行政による観光関連の仕事が多かった。
最初は、その報酬のギャップに驚いた。地方都市のコピーライターが広告の仕事だけで生きていくのは難しい。そういう現実があった。
ともあれ、東京と地方を問わず、広告の世界は、バブル崩壊とともに、企業の広告費が削減され、元気がなくなった。追い討ちをかけるように、デザインの現場ではIT化が進展した。広告費が削減されても、デザイン現場が効率化されれば、利益は確保できるだろう、という甘い見込みのもとに、大小を問わず、マッキントッシュという名のコンピュータが導入された。 もっと安く、もっと早く、もっと上手く…IT化されたデザイン事務所は、コンピュータやプリンタのリース代を稼ぐという負荷もいっしょに手に入れることになる。作業が効率化されたら、その浮いた時間を、考える時間、創造的な思索に振り向けられるはずであった…はずであった、で、あった。
デザイン現場のIT化は必然であり、僕はどちらかと言えば、それを煽動してきた立場にある。まだマッキントッシュに印刷品質の日本語フォントがなかった20年以上前から、この道具の可能性に着目し、デジタルデザインの最前線を個人的に取材してきた。実際にデザイン会社へのMac導入の責任者にもなった。(デザイン業界でMac=マックといえば、それはハンバーガーではなく、コンピュータのマッキントッシュ。)それだけに、道具に使われる使い方をしているデザイナーを見ると、それは当初の理想から大きくかけ離れており、ちょっと残念だ。
世紀が変わり、2007年も後半に差し掛かろうという今、時代を切り取るような広告表現は生まれにくくなっている。バブル崩壊とともに数多くのデザイン会社が倒産し、自然淘汰がひと段落した時代。生き残っているデザイン会社はいずれもチカラのある会社だと思う。
だが、大雑把な分析で恐縮だが、マクロな視点から見れば二極分化したように見える。ひとつはデザイン作業の無駄を排して合理化を徹底する方向性、もうひとつはデザイン表現にこだわりクオリティを追求する方向性。前者は、時代の要請に沿うものであり、そのマーケットも大きいからビジネスとしては人件費の問題さえクリアできれば成立する。しかし、後者は、そのクオリティと報酬のバランスが問題だ。クライアントがその価値を認めてくれるかどうか。クオリティを追求して生き残れる確率は、首都圏でも一握りだが、地方都市なら、なおさら厳しいものがある。
広告黄金時代に青春を過ごし、夢を抱いて、広告業界に入った人々、デザイナー、コピーライター、カメラマンたち、いわゆる広告クリエイターは、いま、その職業に対して表現者としての自負とともに、大なり小なりの危機感がある。好きで選んだ職業ではあるけれど、慢性的なデフレ・スパイラルによって、収益モデルが破綻しはじめているのだ。当然ながら、現代の若者にも、この業界が魅力的ではなくなっている。
広告制作の現場は、いま、大きな転機を迎えているのだろう。従来のビジネスモデルに依存していては、もはや発展が見込めない。まず、広告そのものの意味を根本から問い直し、そして現状の企業をめぐる環境の変化に、広告戦略はどこまで対応できるのか。生活者の消費行動をどこまで洞察できるのか。そのとき、メディアは?手法は?表現は?
広告業界から、クリエイターが消滅する前に、何らかの手を打たねばなりません。そのうち、気がつけばクリエイターはすべて60歳以上、日本の広告会社のトップはすべて外国人だったりして…ね。


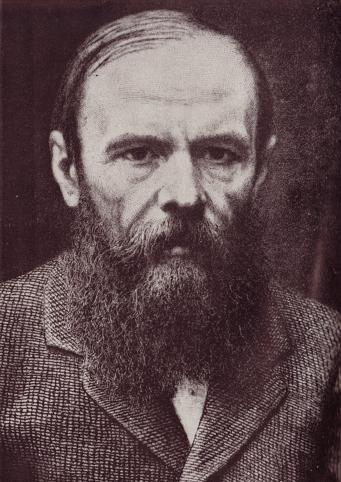

コメント